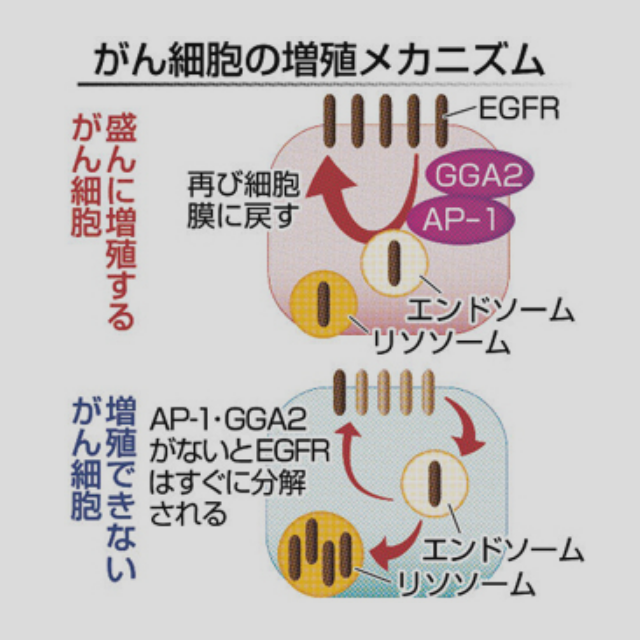肝臓の機能概要
 肝臓には下表のように、いくつかの重要な働きがある。
肝臓には下表のように、いくつかの重要な働きがある。
| 合成能 |
血清たんぱくの主成分であるアルブミン、血液を固める働きのある凝固因子などを合成する。 |
| 分泌能 |
脂質、たんぱく質の消化・吸収にかかわる胆汁を胆管内に分泌する。 |
| 代謝・分解能 |
いくつかのホルモンや薬剤、アンモニアなどを代謝・分解して別の形にしたり、人体にとって無害にしたりする。 |
肝臓は、体の中で最も大きな臓器で、大人では重さ1,000gほど(一般的に、体重×20g)になる。
右の上腹部に位置し、肋骨(ろっこつ)に守られていて、上は横隔膜、下は胃や十二指腸に接している。
解剖学的には、肝鎌状(かまじょう)間膜を境に左右に分けられていて、
手術など実際の治療にあたっては、カントリー線(中央線)と呼ばれる、
下大静脈と胆のうを結ぶラインで分け、左を左葉(さよう)、右を右葉(うよう)としている。
肝臓はまた、「血の固まりでできている」といわれるほど、血液が大変豊富な臓器だ。
肝臓の血管としては、消化管から送られてきた血液を集めた「門脈」、
肝臓に栄養や酸素を送る「肝動脈」、肝臓から流出する血液を心臓に送る「肝静脈」
という太い血管が3本あり、それらの血管から枝分かれした毛細血管が無数に張り巡らされている。
この血管の多さが、肝臓がんの手術を難しくする。
このように肝臓に多くの血管が存在するのは、代謝や解毒などにかかわる多くの役目を担っているからだ。
その役割は500以上にも上るといわれており、肝臓は「化学工場」に例えられる。
もう一つ、ほかの臓器にはない肝臓の大きな特徴は、一部を切り取っても再び成長する、
つまり再生が可能な臓器であるということだ。
肝機能のよい人なら、肝臓全体の3分の2を切除してももとの大きさの90%ほどまでは再生する。
この驚異的な再生能力があるからこそ、肝臓ではドナーから肝臓を移植する、生体肝移植という治療法ができる。
ただし、肝炎などで肝機能が低下するほど、再生能力が落ち、肝硬変になると、再生はほとんど不可能だ。
 肝臓には下表のように、いくつかの重要な働きがある。
肝臓には下表のように、いくつかの重要な働きがある。